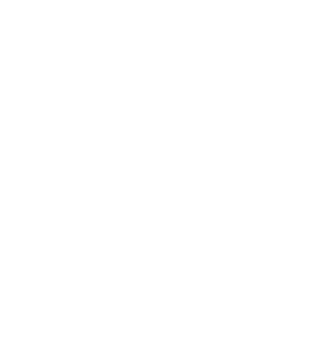Season 3 第6講
日本語は「創(きず)」である
2023.3.4
2022年10月15日に開幕したHyper-Editing Platform [AIDA]Season3。
「日本語としるしのAIDA」に潜る連続講義も、いよいよ最終回の第6講となった。
[AIDA]は、受け取って終わりという一方向の講座ではない。何を受け取りどう考えたか。それぞれの課題や問題意識を持ち寄り、生じた「問い」を突起にして交わし合い、双方向に創発を起こしていくプラットフォーム=場だ。

▲テーブルの上にはSeason3「日本語としるしのAIDA」の参考図書100冊以上が並ぶ。
最終講のこの日、松岡正剛座長をはじめ、ボードメンバー5名も豪徳寺の本楼に集結。座衆(受講生)が半年の集大成として書き上げた「間論(まろん)」をベースに、セッションが行われた。

▲受講生にのみ配布される「月刊あいだ」。最終講仕立てのメディアに変換された、多士済々のボードメンバー。
「問い」が「問い」を生む
座衆は何を問うたのか。何につまづき、どう悩み、どんな気づきを得たのか。進行役の橋本英人(編集工学研究所主任研究員)と吉村堅樹(イシス編集学校学林局林頭)は、座衆の「間論」を紹介しながら、発言を促していく。間論で日本のビジネス環境に対する危機感を吐露したのは、姜舜伊さん(リクルートマネジメントソリューションズ)だ。
「今まで、グローバル資本主義という〝地〟からものを見ていたので、クライアントに対し、その範囲から問題点や施策を議論してきました。ですが、[AIDA]で、私たちのおおもとにある日本語としるしとは何か?を思考したことで、歴史や文化というフィルターを通して、日本や日本におけるビジネス環境を捉え直すようになりました。対話相手や私たちがそもそも立脚する〝地〟をお互いに確認したり、立ち戻るようになったのです。するとクライアントに対して、別の可能性や多義性など、相手の驚きや再発見を促す対話を持ち出せるようになりました」(姜さん)。
所属する「ながめく連」のメンバー内で「いちばん変わった」と評されたのが、この姜さんだった。

2018年から5シーズン連続で[AIDA]に参加する桑原寛文さん(ジェイテクト)は、第5講のゲスト、リービ英雄氏に着目。そこから、日本語と欧米語の差分と日本語の可能性に踏み込んだ。
「グローバル資本主義が席巻する中で日本の良さを活かすには、“遊び”や“小さなコミュニティ”が有効ではないでしょうか」。芭蕉のいう「虚に居て実をおこなふ」ような日本語の持つ遊び、連歌のような小さなコミュニティ。これらはスタンダードルールで定義されたグローバル資本主義の中での日本の強みなると桑原さんは言う。
多くの座衆も日本語の持つ“遊び”に言及した。

ボードメンバーが「その先」に見たもの
座衆の発言や間論の視点をきっかけに、ボードメンバーからは次々と日本語の可能性と現代社会に対する危機感や展望が語られた。
山本貴光「日本語の潜在性に気づくべき」

山本貴光氏は、「日本語の潜在性」に目を向ける。「潜在性」とは可能性のことではない。役に立つ、立たないという二項対立を超えた、日本語の持っている別様の世界のことだ。「潜んでいるにも関わらず、見えていないもの――日本語の潜在性が、日本語と遊ぶことで見えてくるんじゃないか」。例えば枕詞や本歌取りは、日本語の多義性・多様性と遊ぶことで生まれた。「“遊ぶ”とは、ゴールすることではなく、プロセスそのものを楽しむことです。このAIDAは、まさにそれを体現する場になっている」。
武邑光裕「職人も言語化できない〝黒百色〟」

「日本語は曖昧であるからこそ、窮屈な部分もある。日本語としるしの両方を捉える必要がある」と武邑光裕氏。例えば西陣織の職人の間で、「黒百色」という言い方があるという。天然素材で染めるので、同じ原料を使っても微妙に色が異なり、多様な黒色になるのだ。職人は言語化できないその色を「しるし」として捉えていた。
村井純「失われていく言葉をどうするか」
村井純氏は中国が社会主義国家を建設するなかで、縦書きをやめ、横書きに統一してしまったことに言及した。「するとどうなったか。これまで書かれてきた縦書きの文献が省みられなくなり、言語が、ひいては文化がすり切れてしまった」。同様のことは、日本語にも起こりうる。「何を保護し、残していくのか」と村井氏は問いを投げかける。「未来の日本語への責任を、誰が持ちますか?」。
田中優子「私たちはもっと、文化を言葉にする必要がある」

田中優子氏は、歌川広重の『東海道五拾三次 大磯』に言及した。「この浮世絵は『虎ケ雨』と副題が付けられ、曽我の仇討ちがモチーフになっています。大磯を舞台にした曽我十郎と虎御前の悲恋の伝説を描いたものなのですが、そうした背景がわからなくなっている」。それは、その後の日本人が手間を惜しんできたからだと田中氏は言う。「日本語を考える上では、絵やしるしにまつわる文化を、徹底的に言葉にしていく必要があるんじゃないか」。

歌川広重の『東海道五拾三次 大磯』 出典:東京富士美術館
大澤真幸「世界に追随して安全運転しているだけでいいのか」

大澤真幸氏は「どうもみなさんの話を聞いていると、危機感が足りないように思える」と座衆たちを見据えた。「先日、藤井聡太五冠の将棋を観ていたが、AI評価値〈1%-99%〉まで追い込まれていた。このまま最善手を続けても、勝ちは見えない。藤井五冠はどうしたと思います? あえて最善ではない手を指し、一気に形勢を逆転したんです」。いま世界は危機にある。世界のルールに従い安全運転を続けても、一緒に終わっていくだけ。日本語という特殊性を手に、「既存のルールを飛び越える手を指すことが必要なのでは?」
日本語は「創(きず)」をつける
「日本語は“創”である」。松岡座長は最後にこう切り出した。
「創は、アーカイブの場ある『倉』と、刀を表す『刂』から成り立っています。創は、アーカイブ(倉)を刀で掻き回すという意味なんです」。

外から入ってきた漢字や概念を、そのまま受容せず、いったん倉に入れ、そこでかき混ぜる。日本語として変容させるのだ。そこにはいくつもの「すき」(数寄、梳き、隙)が生まれる。変容されたものがかたちとなり、名付けられたのが、連歌や能、俳句といった文化装置であり、あるいは、征夷大将軍、執権、老中といった日本独自のロールだった。
「今の日本に、次々と新たなロールを編集し、外来のコードを変換する受け皿はありますか?」と松岡座長。
ではどうするか。「日本語としるしのAIDA」で問うてきたのは、まさにこのことだったかもしれない。日本の編集力が、いまこそ問われているのだ。
座衆はこの場から生まれた大きな「問い」を携え、それぞれの課題へと向かっていく。

▲この日の本楼。Season3を終え、次の2023年秋の開幕を待つ。