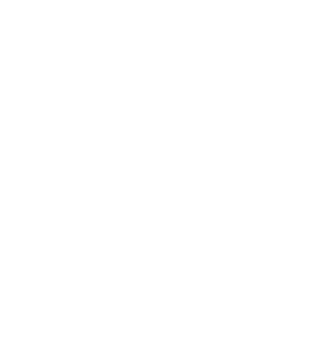[AIDA]ボード・インタビュー第6回 座長 松岡正剛
「日本語としるしのあいだ」をめぐって
日本には「知のコロシアム」がある。その名はHyper-Editing Platform[AIDA]。ここは、松岡正剛座長と多士済々の異才たちとともに思索を深め、来たるべき編集的世界像を構想していく場だ。
2022年10月〜23年3月に実施したSeason3のテーマは「日本語としるしのあいだ」。日本語の謎に迫ることは、すなわち「方法日本」を探ることでもあ
*この記事は、受講者限定メディア「月刊あいだ」に掲載したものです。ボードメンバーのインタビューを特別公開します。
松岡正剛/座長
1944年、京都府生まれ。早稲田大学文学部中退。オブジェマガジン「遊」編集長、東京大学客員教授、帝塚山学院大学教授などを経て、 現在、編集工学研究所所長、イシス編集学校校長、角川武蔵野ミュージアム館長。 80年代「編集工学」を創始し、日本文化、経済文化、物語文化、自然科学、生命科学、宇宙、デザイン、意匠図像、 文字などの諸分野をまたいで関係性をつなぐ研究に従事。 その成果を、様々な企画、編集、クリエイティブに展開。 一方、日本文化研究の第一人者として私塾を多数開催。 2000年、壮大なブックナビゲーション「千夜千冊」の連載を開始。 同年、eラーニングの先駆けともなる「イシス編集学校」を創立した。 近年は「松丸本舗」「近畿大学アカデミックシアター」「角川武蔵野ミュージアム」など本を媒介にした数々の実験的プロジェクトを展開。
日本という方法が、世界を解き明かす
――Season3は「日本語としるしのあいだ」がテーマでした。
松岡: 僕自身は昔から、言語に限らず「線の発生」や「声の出現」などなにかのスタートに関心をもっています。人間は言葉をもちました。ではなぜ、言葉ができたのでしょうか。その起源を探るとき、私たちは困ったことにその「言葉」を使わざるを得ないんです。我々は世界の原点を考えるとき、すでに私たちがもっているツールを使ってルーツを遡らないといけないんです。
物事のおおもとがなんであったか、それを長年考えていると、あることに気が付きました。いまの状態には「かつてそうだったもの」が影響を与えているということです。プラトンがアトランティスを空想したり、老子が太極が陰と陽に分かれたときを想像したように、編集工学でも「すこし手前のもの」を想定することをしてきたんです。私が千夜千冊を書いたり『情報の歴史』を作ったりしたのも、そのスタディの一環ですね。
――第1講では、日本語をのおおもとを知るためには「源氏物語」を解く必要があるとおっしゃっていました。
松岡: 源氏物語を書いたとき、紫式部の家は落ち目でした。しかし、ひと昔前は輝かしい時代だったわけです。紫式部は、「いずれの御時にか」と書き出すことで、かつての時代のことを混ぜながら物語をつくったのです。このような編集構造を彼女は用意した。そこに「日本語としるしのあいだ」を考える切り口があるかなと思っています。
――なるほど。座長は「虚にいて実をおこなうべし」という芭蕉の言葉も引用されていました。西洋的な言葉は制度的な「実」を行うのに長けていて、日本語は「虚」に力があるのかなと考えたのですが。
松岡: ローマや中国にあった「帝国」は、法的な言語と社会的な制度をつくりあげました。帝国の周辺には、2種類の地域が出現します。いまのウクライナやチベットなど帝国の弾圧を受ける地域と、そのような影響を受けにくい地域です。日本列島は、地政学的にいえば「極東(far east)」であったがゆえに、帝国的なものを受け入れつつ、自分たちの自由さを残せたのだろうと思います。それは言語だけではありません。
――大陸から入ってきた稲も、直播きではなく苗代を開発するなど工夫をしましたね。
松岡: そうです。そうすることで、本居宣長の言葉でいえば「ただの詞」と「あやの詞」を共存させることができたのです。たとえば、日本は、唐の律令制度を学んで「法的な言葉」を取り入れました。けれども、縄文以来、心のなかをうごめいていた思考や表現などの「心内語」はにはその影響が及ばないようにして、和歌などの形式で保存ができた。このことが大きかったのだと思います。
律令制を取り入れても、藤原道長から白河法皇まで中国的な制度とは異なるかたちで政権を握りましたし、その後は武家が台頭してくることになった。そうして登場した平清盛や西行法師は、中国のモデルとは違うキャラクタリゼーションを起こしたんですね。清盛は武家でありながら貴族的、西行は貴族でありながら歌人でした。
――しかし明治維新や敗戦では、外からの文化をかなり受け入れてしまいましたね。
松岡: 僕の感覚でいうと、心内語として歌を残すという感覚は夏目漱石あたりで途切れてしまったように思います。戦後になると、英語がそのまま使われるようになりましたしね。
――西欧のコードを大量に受け入れたのは、編集がおいつかないほど量が多かったからなんでしょうか。
松岡: それもありますが、日本がヨーロッパに対して決して追いつかない部分があります。それは、論理思考のためのツールとして言語以外に「数学」を作ったことです。数学の誕生とサイエンスの出現に関しては、日本は西洋に学ぶべきです。
しかしだからといって、母語に日本語をもった私たちが、日本文化を考えるときにまで西洋の方法を使うべきだとは思いません。ニュートンやライプニッツ、ベーコンやダーウィンの思想で、日本のことをすべて考えるのは無理だと思います。
たしかにサイエンスや数学は重要で、レヴィ=ストロースがブルバキの数学を使って構造主義を発展させたのは確かに素晴らしかった。けれども、我々も「日本という方法」を使って、世界や科学のことを考えられる。それこそが、西洋のサイエンスに代わりうるものだと信じています。僕がイシス編集学校を「方法の学校」と呼んだり、21世紀を「方法の時代」と呼んでいるのはそういう意味なんです。
――ボードセッションでは「日本語の特殊性こそが普遍性につながる」という発言もありました。
松岡: たしかに、日本語がもってしまった宿命というのはあります。いまだ、西洋では複雑なものをなるべく排除して考えるようにしていますが、最近の科学では、宇宙にダークマターが70%も存在するなど、解読不能なものが奥に眠っていることが判明してきました。「ただの詞」と「あやの詞」をもちつづけた日本語ではそこにアプローチできる可能性があります。清水博や津田一郎などの科学者はそのことに気づいているでしょうし、ファッションにおいてモノクロームで対抗したヨージ・ヤマモトもそうです。日本語の可能性を信じているのは僕だけではありません。
タブロイドおよびアイキャッチデザイン:穂積晴明
タブロイド撮影:後藤由加里
インタビュー記事構成:梅澤奈央
「月刊あいだ」編集長:吉村堅樹
AIDAサイト編集:仁禮洋子
(以上編集工学研究所)
AIDA ボードメンバーインタビュー
第1回:デジタル庁顧問・村井純さんインタビュー「日本語がインターネットの未来を決める」
第2回:法政大学名誉教授・田中優子さんインタビュー 自然とつながる「しるし」を残すために
第3回:大澤真幸さんに聞いた「資本主義を乗り越える 日本語的発想とは」
第4回:文筆家・ゲーム作家山本貴光さんに聞いた「漢字の罠」とは
第5回:メディア美学者・武邑光裕氏インタビュー〜メタヴァースは〈マ〉を再生するか〜
第6回:座長松岡正剛インタビュー「日本語としるしのあいだ」をめぐって