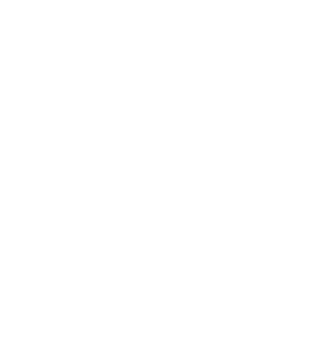AIDA Season2 ボードメンバー「メディアと市場のAIDA」見方集
大澤真幸、田中優子、佐藤優、武邑光裕、佐倉統、山本貴光、村井純ー。Hyper-Editing Platform[AIDA]シーズン2の第1講、ボードメンバー7名が、豪徳寺・本楼にある巨大なブビンガテーブルを囲み、一堂に会した。
Season2のテーマは「メディアと市場のAIDA」。メディアとは何か?市場とは何か?メディアと市場の「あいだ」に何を問うべきなのか?
メタバース、遊郭、デジタルゲーム、国家、ドーピング、インターネット、資本主義。次々と様々なジャンルのキーワードが繰り出され、絡み合い、結びつきながら、侃侃諤諤のディスカッションが交わされた。
本記事では、ボードメンバーの発言をそれぞれ約400字にダイジェスト編集した。7名は「メディアと市場のAIDA」をどう見るか。
*同日行われた松岡正剛座長講義「なぜ今“メディアと市場のAIDA”を考えるのか」も合わせてご覧ください。
大澤真幸「資本主義は終わるのか、終わらないのか?」
「メディア」と「市場」を合体させると「資本主義」になる。いま世の中では、この資本主義をめぐって、2つの感覚が無意識的にせめぎ合ってると思う。
一つは「資本主義は終わらない」という感覚、もう一つは「いや、終わるかもしれない」というまったく逆の感覚だ。
資本主義は、ユダヤ・キリスト教的想像力の中から生まれた。つまり、終末論と相性がいい。ずっと「終わりとの葛藤」を繰り返してきた。歴史的には20世紀末の冷戦終結とともに、資本主義は永遠のシステムになったかのように思われた。
フレドリック・ジェイムソンは、資本主義の終わりを想像することは、世界の消滅や人類の滅亡を想像するよりもずっと難しいと述べている。
だが、資本主義という概念がいまだ死語になることなく、人々を魅了し続けているのは、なぜか。絶対に終わるはずのない資本主義もやはりいつか終わるかもしれないという感覚が完全には消え去らなかったからだ。
はたして資本主義とは異なる選択肢というものはありえないのだろうか。
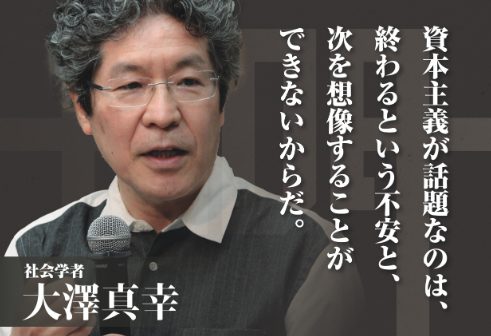
田中優子「メディアの本来は、神と人の媒介者」
メディアという言葉は「メディウム」の複数形である。そのメディウムとはシャーマンのこと、つまり媒介者を意味する。本来、メディアは神と人間の間、自然と人間の間を媒介する者だった。
そのとき、例えば布などが「媒介物」になる。それは独特の力を持ったものとして位置付けられる。ところが、メディアが人と人との間のものになったとき、「商品化」がおこる。商品は大量生産するために標準化され、定価がつく。
価格をつける方法は定価だけではない。定価のない社会が実は長かった。たとえば、お茶の箱書き。茶碗の入っている箱に誰がいつどの茶会で使ったのかを記録する。それが積み重なっていけばいくほど価値が高くなる。茶碗そのものは変わらないが、箱書きが特別な価値を与える。想像力によって価格が変動する。
「悪所の経済」というものもある。江戸時代の遊郭や芝居小屋では、オモテからは見えない闇のお金の動きがあった。客との間に立つのは茶屋だ。この茶屋が采配する経済にも定価がない。闇の世界から様々な価値の刺激を受けて、浮世絵をはじめメディアのイノベーションも次々と起こった。

佐藤優「国家や宗教の、外部に目を向ける」
メディアと市場の「あいだ」を議論するためには、否定神学的にむしろ「外部」に目を向けてなくてはいけない。たとえば、国家。国民が分散化し、個人的なやりがいに関心を向けていくと権力者にとっては都合がいい。民主主義的な手続きが軽視されれば、権力者に白紙委任状を与えてしまうことになる。
国家の背後には警察力、検察力があり、軍隊の力がある。経済安全保障の名のもとに、ビジネスの経済合理性とは異なる基準で国家が介入してくる可能性はいくらでもある。権力論あるいは国家論への回路は軽視できない。
また、AIDAでの議論は基本的にユダヤ・キリスト教文明のコード体系の中で進んでいるが、その「外部」に対しても思いを寄せる必要がある。たとえば、カール・バルトやハンス=ゲオルグ・フリッチェといった神学の思想から良いヒントが得られるかもしれない。
あるいはカール・ユングの『心理学と錬金術』。西洋文明の裏の思想を担う錬金術は、未知なるものを未知なるままに、分かりにくいことをより分かりにくく話すという説明法をとる。

武邑光裕「メディア”こそ”メッセージだ」
ユルゲン・ハーバーマスは、18世紀の市民社会において、人々は言論や出版の自由を得て、対等な討論によって政治参加できる理想的な「公共圏」が生まれていたことを指摘している。コーヒーハウスやサロンのような文化もこのときつくりあげられた。
21世紀の初頭、ソーシャルメディアがこの「民主主義の夢」を代替するのではないかと期待された。これがことごとく失敗に終わった原因をハーバーマスは「生活世界の植民地化」にもとめる。つまり、システムが生活世界もろとも全域的に侵蝕していった。
「THE MEDIUM IS THE MASSAGE」と言ったのはマーシャル・マクルーハンだ。ソーシャルメディアもその他のデジタルメディアも、コンテンツと切り離して、市場の中で巨大な影響力をもつメディアとして考える必要がある。マクルーハンの言葉は、日本では「メディアはメッセージである」と訳されているが、「メディア”こそ”メッセージだ」と翻訳すべきではないか。

山本貴光「ゲームはメディアであり、市場でもある」
マイクロな時間とマイクロな欲望とマイクロな注意力を絶えず収奪してお金に変換するマシンこそがデジタルゲームだ。根本的には計算可能なものしか扱えない。どんなゲームであれ、クリエーターの想像力の限界がその世界の限界になっている。
だが、独自のルールを持ちこみ、セカンド・オーダーを設定することでゲームの可能性は新たに開かれていく。現実の政治的・経済的な仕組みを実験することもできる。
現実世界では、遊びやゲームのルールをどんどん切り替えながら、それに合わせて別々のキャラクターをロールプレイするという行為はますます日常化している。
ポルトガルの詩人・フェルナンド・ペソアは、私たちが今、デジタルワールドの中で巻き込まれつつある状況を意図的に生み出し、それを駆使して創作に向かった。ペソアは「異名(heterónimo)」と呼ぶ、およそ70もの人格をつくりあげ、それぞれのマイクロ・パーソナリティーを著者として創作するスタイルを確立した。
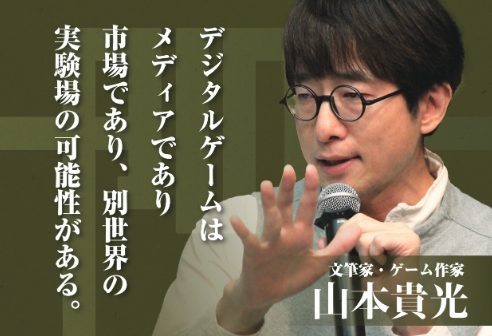
佐倉統「近代国家の次なるシステムは設計可能か?」
情報の価値はどのように決まるのか。どう決めるべきなのか。たとえば、スポーツではドーピングの境界が問題になる。トレーニング器具は許せるのに、薬物が許せないのはなぜなのか。パラリンピックの義足の選手を応援したくなるのはなぜなのか。
その価値を決定する文脈を支えるシステムが国家であり、文明なのだろう。そのような信頼を支えるシステムとして、EUでもGAFAでもなく、近代国家の次なるシステムやサブシステムを設計することはできるのだろうか。このとき、日本や日本人の特性というものをどのようにすれば活かすことができるのか。
国家とは何か。日本とは何か。私とは何か。それぞれのイメージは個人によってきわめて多様であるはずだ。この個々のイマジネーションとクリエーションを情報社会、情報技術の中でどういうふうに折り合いをつけていけばいいのか。

村井純「経済こそ、国家から自由になるための鍵」
インターネットはグローバルな空間を創造した。いま世界の全人口の約60%がインターネットを利用している。2000年は6%程度だった。あと5年もすれば、100%に達するだろう。
インターネットを支える主なインフラは海底ケーブルだ。海底ケーブル敷設の駆け引きは地政学上の鍵を握るインターナショナルな問題である。北極海の氷の融解、衛星インターネットなどを発端に、世界ではインターネットインフラをめぐるとんでもないゲームチェンジが起き始めている。
グローバルな空間はインターナショナルな空間に接続された。だが、この地球でただひとつの自由空間を守るためには、できるかぎり国家権力の関与を避けなくてはならない。では、どうすれば「グローバルな意思決定」は可能になるのか。
ヒントは「E」。Economy の「E」である。実はOECD、APECなど「E」のつく国際組織とはインターネットガバナンスの価値観を共有することができる。「市場」こそがエントリーの切り札になる。